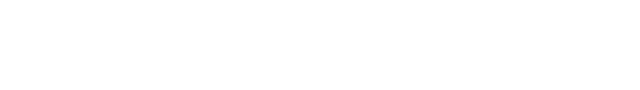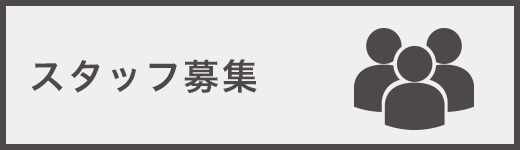肥満症(肥満外来)
肥満症とは(定義)
「肥満」とは脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数(BMI = 体重 [kg] / 身長 [m]²)≧25 の状態を指します。日本では、標準体重はBMI22kg/m²とされています。これは、BMI22kg/m²程度が最も死亡率が低い(長生き)という国内からのデータに基づいています。
「肥満症」とは肥満に関連する健康障害を合併するか、もしくはその合併が予測され、医学的に減量を必要とする状態です。
肥満症 診断基準
肥満と判定されたもの(BMI≧25kg/m²)のうち、以下に示す「肥満症の診断に必要な健康障害」を合併する場合に、「肥満症」と診断します。
- 耐糖能障害(2型糖尿病、耐糖能異常など)
- 脂質異常症
- 高血圧
- 高尿酸血症、痛風
- 冠動脈疾患
- 脳梗塞、一過性脳虚血発作
- 非アルコール性脂肪性肝疾患
- 月経異常、女性不妊
- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満低換気症候群
- 運動器疾患(変形性関節症、変形性脊椎症)
- 肥満関連の慢性腎臓病
肥満の状態であると、上記の疾患を発症しやすいことが知られており、この中でも特に糖尿病の発症に肥満が関わっていることが知られています。
肥満と糖尿病の関係
膵臓から出るホルモンである「インスリン」が糖を血液中から細胞内に取り込んでいます。
「糖尿病とは」でご説明していますが、糖尿病とは「インスリン」が十分に働かないために血液中から細胞内にブドウ糖を取り込めず、それにより血液中のブドウ糖濃度が高い「高血糖」の状態が持続する疾患です。
肥満の状態だと糖尿病になりやすい理由ですが、肥満になると「インスリン」の働きが鈍くなることが知られており、これにより高血糖の状態になってしまいます。
肥満の原因
肥満の原因は、原発性肥満と二次性肥満に分類されます。
肥満の原因が明らかなものが二次性肥満で、明らかな単一の原因がはっきりしない肥満を原発性肥満と分部位します。
肥満症のうち、原発性肥満が90%以上と言われていますが、厳密な統計データは現時点ではありません。
主な二次性肥満の原因として内分泌疾患、薬剤性、遺伝性などが知られており、生活習慣の改善を行っても肥満が十分に改善しない場合には、これらの可能性を検討します。
肥満のタイプ
肥満は、内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満という2つのタイプに分けられます。
特に内臓脂肪型肥満が問題で、内臓脂肪により上述の「インスリン」の働きが悪くなり糖尿病になりやすくなります。糖尿病に加えて、高血圧や脂質異常症なども合併しやすくなり、これらが合併する「メタボリックシンドローム」の状態になりやすくなります。
内臓脂肪型肥満ですが特に中高年の男性に多く、お腹がぽこっと出ていることが特徴的です。
肥満度
肥満度の判定は、以下に沿って行われます。
特に、BMI35kg/m²以上では高度肥満と定義され、より厳格な治療が必要です。
| BMI (kg/m²) | 判定 |
| BMI < 18.5 | 低体重 |
| 18.5 ≤ BMI < 25 | 普通体重 |
| 25 ≤ BMI < 30 | 肥満 (1 度) |
| 30 ≤ BMI < 35 | 肥満 (2 度) |
| 35 ≤ BMI < 40 | 高度肥満・肥満 (3 度) |
| 40 ≤ BMI | 高度肥満・肥満 (4 度) |
肥満症外来(ダイエット外来)の治療目標
肥満症の治療において、減量は目的はなく手段です。治療目標は、体重を落とすことにより合併する疾患(高血糖、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症)などが改善し、それにより健康寿命を長くする(心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを減らす)ことになります。脂肪中でも、特に内臓脂肪を落とすことが健康寿命の延伸に重要です。
一方、内臓脂肪減らしつつ筋肉量を維持することも健康寿命の延伸に重要です。
また、健康寿命が長くなることにより個人の「生活の質」が改善し、より満足した生活を送れることも期待できます。
具体的な減量目標ですが、肥満症(BMI25-35kg/m²)ではその時点の体重から3%以上の減量、高度肥満症(BMI35kg/m²以上)ではその時点の体重から5-10%の減量を目標とします。
以下の流れに沿って治療を行うことが推奨されています。
肥満症診療ガイドライン2022より引用
肥満症 治療
肥満症 の治療の基本は食事療法です。それでも不十分な場合には薬物療法や外科的治療が検討されます。
運動療法は減量するためには効果は不十分であるとされていますが肥満の予防には有用で、減量した後の体重の維持には有用です。
減量がうまくいって体重が落ちても、リバウンド(体重増加)することも多いため、食事療法と運動療法を継続していくことが重要です。
肥満症 食事療法
肥満症(BMI25-35kg/m²)では、1日の摂取エネルギー量の算定基準は25 kcal × 目標体重(kg)以下にすることが推奨されています。目標体重の目安は65才未満ではBMI22kg/m²程度、65才以上ではBMI22-25kg/m²程度の体重とされています。
エネルギー量の内訳は、炭水化物50〜65%、蛋白質13〜20%、脂肪20〜30%が目安とされています。ただし、体重減少には糖質(炭水化物)制限が有効なので、糖質をさらに制限しても良いかもしれないという報告もあります。
内臓脂肪減らしつつ筋肉量を維持することも重要なので、必須アミノ酸を含む蛋白質、ビタミン、ミネラルを十分に摂取することが勧められています。
肥満症 運動療法
上述の通り運動療法は減量するためには効果は不十分であるとされていますが、肥満の予防には有用です。また、運動により死亡のリスクや心筋梗塞、脳梗塞などの心血管疾患のリスクを下げることができるので、肥満治療においても非常に重要です。
具体的な内容としては、以下が推奨されています。
・有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)を中心に行い、レジスタンス運動(スクワットや腕立て伏せなど)の併用も望ましい。
・軽~中強度の運動を1日30分以上行い、週150分以上確保する。
肥満症 薬物治療(治療薬)
保険適応について
肥満治療薬の新薬であるウゴービ(GLP-1受動態作動薬)が2024年2月より発売されました。この新薬は、保険適用で使用できるようになっています。しかしながら、現時点では保険診療で処方できるのは大学病院や総合病院に限られます。
さらに、保険適応が認められているのは以下を満たす患者さんに限ります。
日本肥満学会より引用
要約しますと、以下の場合に保険適応になります。
・BMI が 27 kg/m2 以上であり、2 つ以上(高血圧、脂質異常症又は 2 型糖尿病を含む)の肥満に関連する健康障害を有し、食事/運動療法で十分な効果が得られない場合。
・BMI が 35 kg/m2 以上であり、高血圧、脂質異常症又は 2 型糖尿病のいずれかを有し、食事/運動療法で十分な効果が得られない場合。
これらに該当するかがに関しては、総合病院にご紹介させて頂きます。
ダイエット目的で「痩せ薬」として使用することの問題点
近年、このGLP-1受動態作動薬は美容クリニックなどにおいて「痩せ薬」として不適切に使用されている事例が問題視されており、本来の使い方と違う使い方で宣伝されていると問題視されております。そのため、厚生労働省や各学会より適正使用のための注意喚起がされております。
問題視されている理由として、以下があります。
・GLP-1受容体作動薬が美容目的に使われてしまい、本来必要な糖尿病の患者さんが使えなくて困っている。
・GLP-1受容体作動薬を美容目的で服用した場合のデータがなく、肥満症の方に使用した場合と比べて副作用が多いかなど、安全性が明らかでない。
・「自己責任の上で自由診療を行います。」という同意を患者さんから取っている医療機関もあり、重篤な副作用が起きた場合にも表に出にくくなっている。
保険適応外のGLP-1受容体作動薬の使用に対する当院のスタンス
今後のエビデンスの蓄積が待たれますが、現状では当院は美容目的のGLP-1受容体作動薬の処方は行いません。GLP-1受容体作動薬を服用することにより健康寿命延伸の恩恵を受けらる可能性が高い方に限り使用するべきと考えています。
上述の「BMI22kg/m²程度が最も死亡率が低い(長生き)」という国内からのデータもある通り、少なくともBMI22kg/m²未満の方に関しては投薬すべきでないと考えております。
一方、現状の保険適応である「BMI27 kg/m2 以上かつ、2 つ以上(高血圧、脂質異常症又は 2 型糖尿病を含む)の肥満に関連する健康障害を有する」に満たなくても、使用することによりメリット(健康寿命の延伸の期待)がデメリット(副作用のリスク、金銭的負担)を上回る人もいると考えます。
特に糖尿病、脂質異常症、高血圧、痛睡眠時無呼吸症候群、メタボリックシンドロームなどの内科慢性疾患をお持ちの方に関しては減量することで病状の改善が期待できます。
まずは上述の食事療法、運動療法の指導をさせて頂いた上で、メリット(健康寿命の延伸の期待)がデメリット(副作用のリスク、金銭的負担)を上回ると主治医が判断した場合に限り処方をさせて頂きます。迷う場合には、一度ご相談頂けますと幸いです。
いかがでしたでしょうか。名古屋で肥満外来をお探しであれば、是非金山駅前の当院への受診をご検討ください。
食事の具体例として、健康上寿ネットの肥満治療の食事レシピも大変参考になりますので、一読をお勧め致します。
参考文献:肥満症診療ガイドライン2022、日本糖尿病学会「GLP-1受容体作動薬およびGIP/GLP-1受容体作動薬の適応外使用に関する日本糖尿病学会の見解」、日本医師会「糖尿病治療薬等の適応外使用について」、厚生労働省「医療広告ガイドライン」、日本肥満学会「肥満症治療薬の安全・適正使用に関するステートメント」
この記事の執筆担当者:中村嘉宏(総合内科専門医)